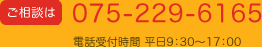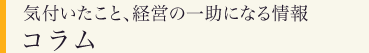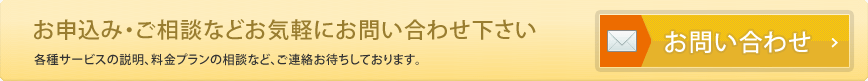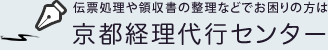多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。
2012年7月アーカイブ
23年度査察は192億円の脱税を把握
いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調
査され、検察当局に告発されて刑事罰の対象となる。国税庁がこのほど公表し
た今年3月までの1年間の平成23度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件
は前年度より1件少ない195件、脱税総額は前年度を約56億円下回る約192億円
だった。1件当たりでは同1,300万円少ない1億200万円。検察庁に告発した件数
は前年度より39件少ない117件となった。
平成23年度1年間に全国の国税局が査察に着手した件数は195件、継続事案を
含む189件(前年度216件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、
うち61.9%(同72.2%)にあたる117件(同156件)を検察庁に告発した。この
告発率61.9%は、前年度を10.3ポイント下回り、38年ぶりの低水準となった。
リーマン・ショック以降の経済状況の悪化により、大型の脱税事件が減少し
たことが要因とみられている。告発事件のうち、脱税額(加算税を含む)が
3億円以上のものは前年度を5件下回る10件、脱税額が5億円以上のものは同3件
下回る3件だった。
近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、23年度の脱税総額
192億円は、ピークの昭和63年度(714億円)の約27%にまで減少している。
告発分の脱税総額は前年度を約56億円下回る157億円、1件あたり平均の脱税額は
同300万円減の1億3,400万円となった。
告発件数の多かった業種・取引(5件以上)は、「建設業」が9件で最多のほ
か、「商品・株式取引」と「人材派遣業」がともに7件、「食料卸」と「情報
提供サービス」がともに6件、「運送業」と「クラブ・バー」がともに5件で続
いた。経済社会情勢を反映し、21年度15件、22年度13件と、この数年間多かっ
た不動産業が減少する一方、「食料卸」や「情報提供サービス」での告発が目
立った。
大阪・泉佐野市が「犬税」の導入を検討
大阪府泉佐野市の千代松大耕(ひろやす)市長はこのほど、犬のふんの放置が
市内の環境を悪化させているとして、その清掃等に充てる費用を賄うために、
「犬税(仮称)」の導入を検討していることを明らかにしました。早ければ2年
後にも条例を制定する方針です。総務省によると、犬税はかつて戦後の一時期
に地方税として存在していました。しかし、現在、飼い犬に対する課税を行っ
ている自治体はないということです。
犬のふんの放置問題は、都市部の自治体の悩みのタネとなっています。飼い
主にマナーやモラルの向上を求めることが第一ですが、強制力がないためにト
ラブルは後を絶ちません。泉佐野市では、2005年に環境美化推進条例を制定し
て、ペットのふんの放置やたばこの吸殻のポイ捨てを禁止しました。違反した
者には1,000円の過料を課すことにしています。しかし、実際の徴収例はなく、
アナウンス効果も上がっていないということです。
こうしたことから千代松市長は、美しいまちづくりを進めるために、今後の
2年間でマナーが改善されない場合、「犬税」を創設すると市議会に説明しま
した。税収はパトロールや清掃作業の費用に充てるということですが、具体的
な課税標準や税額はまだ明らかになっていません。
犬税は、1960年代には約2,700の市町村が導入していましたが、その後、法
定外税の整理が進み、課税団体はなくなっていました。しかし今回、再び脚光
を浴びたかたちとなったのです。
泉佐野市は人口約10万2,000人、約4万4,000世帯で、現在登録されている犬
は約5,400匹あまり。同市は、連結実質赤字比率、将来負担比率がともに早期
健全化基準以上となっており、2010年2月に財政健全化計画を策定しました。
少しでも税収を稼ごうと、今年4月に総務相の同意を得て関西国際空港の連絡
橋を利用する行為に対して課税する法定外普通税「空港連絡橋利用税」を創設
したばかりでした。
日本航空再建の秘訣
新聞誌上で、日本航空の再建とアメーバ経営が話題になっています。
京セラのアメーバ経営は、ひとり一人が経営者になって会社を経営していくものです。
つまり、社員が経営者意識をもって行動していくような経営システムを、
日本航空にも取り入れたのです。
ところで、経営者意識を社員にもってもらうことは、非常に難しい問題です。
多くの社長が、この難問に対して嘆いたり苦しんだりしておられるのです。
しかし、フッと気づくことがあります。社員が退職して会社を興し、
何ヶ月後に偶然出会えば、立派な経営者になっていることがあります。
そうなのです。脱サラすれば、どんな社員でも自然と経営者意識が身についてくるものです。
何故こんな風に、人は変わるのでしょうか。
脱サラすれば、最初はお金の余裕なんてありません。
そのため何としても採算を合わすために、売上を最大に、経費を最小にして、
利益がでるように行動していきます。
また最初の頃は信用なんてありませんから、簡単に銀行からお金を借りることもできません。
そのため、少しでも早く得意先からお金をもらうように努力し、
資金繰りに注意を払って経営していくものです。
不思議なことですが、社員として働いている時には難しい言葉であった経営者意識が、
脱サラすればこのように当たり前になってくることがあるのです。
こんな風に考えていきますと、社員に脱サラするのと同じ心境になってもらえるような、
経営システムをつくっていけばいいということがわかります。
これをどのようにつくっていくのかが非常に難しい問題なのですが、
この難問を見事に解き明かしてくれたのが京セラのアメーバ経営のシステムではないでしょうか。
新興国メーカーが参入できない分野を中核事業に
小川 紘一(東京大学ものづくり経営研究センター特任教授)
1. 日本メーカーが研究開発した技術が、新興国に伝播するスピードが加速している。
技術がマイコンの組み込みソフトや、製造装置の中に蓄積され、新興国に流通するようになったからだ。
技術がいとも簡単に伝播し、新興国との間で技術力に差をつけるのが難しい状況では、
国の制度や企業の経営を変革することが競争に打ち勝つために重要となる。
2.また、自社の強みを見極め、そこに注力する方向に経営をシフトしなければならない。
日本メーカーは一般に、付加価値の最大化につながると信じて、あらゆる事業を内部に抱え込もうとする。
雇用を守るためにも、幅広く事業を維持し続けたいという経営者の気持ちも分かる。
ただ、その結果、オーバーヘッドのコストが非常に重くなっている。キャッチアップする側は、必ず、価格競争を仕掛けてくる。
勝つためには、本当に守るべき事業を決めて、それ以外の事業は外部の会社に任せるようにした方がよい。
3.新興国メーカーが簡単には参入できないような分野を見つけて、中核事業に位置づけるというのも、生き残り策の1つだ。
三菱電機や東芝、日立製作所は家電事業から、社会インフラなどに主軸を移すことで、現在は比較的業績が堅調に推移するようになった。
一方、パソナニックなどはテレビ事業を中核に位置づける経営から脱却できず、経営不振が深まった。
以前とは産業構造が変ったことを認識し、経営も革新していくべきだ。
- 最新コラム
- カテゴリー
- アーカイブ