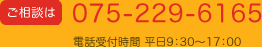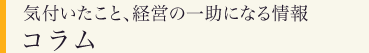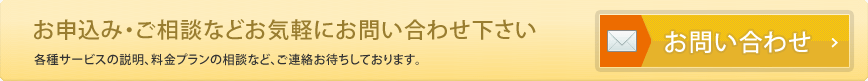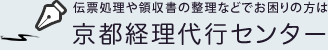多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。
カテゴリー:税務について
報酬に関する源泉所得税
復興特別所得税が平成25 年の1 月1 日からかかるようになりました。
給料などはスムーズに進んだようなのですが、
意外と問い合わせが多かったのが、「報酬に関する源泉所得税」の部分でした。
引き忘れてしまった、どうしよう、といった問い合わせが何件も入りました。
なので、ここで一度もう一度確認をしておきます。
報酬には今までの税率に2.1%の税率を乗じることになります。
例えば報酬料金として111,111円支払う際の源泉徴収事務の場合、
従来であれば所得税率は10%であったので
● 111,111円(支払金額)―11,111 円(源泉徴収税額)=100,000 円
と計算すれば済みます。ところが、これに合計税率10.21%が適用されると
● 111,111円(支払金額)×10.21%(合計税率)=11,344 円(1 円未満切捨て)
となり、結局
● 111,111円(支払金額)―11,344 円(源泉徴収税額)=99,767 円
と計算されることになります。
手取り額から計算する、グロスアップ計算ですと
例えば手取りで 100,000 円を相手に支払いたい場合の納付すべき所得税及び
復興特別所得税の額については、次の算式により求めることができます。
(支払金額)
(1円未満切捨て)
● 100,000円 ÷ (100-10.21)% =111,370円(1 円未満切捨て)
(所得税及び復興特別所得税の合計額)
● 111,370円 ×10.21% =11,370円(1円未満切捨て)
以上より、支払金額は111,370円で納税額11,370円。
手取りは100,000円となります。
また、時期の問題ですが、給与に関しては平成 24 年中に確定した給与で
未払いのものを、平成25年に支払い源泉徴収するときは、
復興特別所得税の対象外になります。
ところで給与については支払日によってその年分の所得とする措置が
認められていますが、この場合、12 月分の給与を 1 月 10 日に支払ったときは、
1 月 10 日の給与は平成 25 年分の所得になり復興特別税の対象になるので、
新しい源泉徴収税額表に基づいて徴収をすることになります。
報酬などに関しては平成 24 年 12 月分までの報酬は復興特別所得税の
対象外ですが、平成 25 年 1月分以降の報酬は、復興特別税の対象となります。
給与と違い「月分」で変わるので、注意が必要です。
請求書などで、何月分のものかわからない場合は、
支払先に確認したほうがよいでしょう。
「がん保険」の税務上の取扱について
法人が自己を保険契約者、従業員を被保険者とした
終身保障タイプの「がん保険」の税務上の取扱は、
「法人契約のがん保険(終身保障タイプ)・医療保険
(終身保障タイプ)の保険料の取扱について」
(法令解釈通達。平成23 年8 月10 日法個117)により、
終身払込の場合は保険料の払込の都度全額損金の額に
算入することとされていました。
したがって、払込保険料の全額が損金算入され、なおかつ、
解約返戻金が高いところから、企業の節税効果が高く
節税型保険商品の代表として人気がある保険でした。
ところが、終身タイプのがん保険は保険期間の中途で
解約した場合に多額の解約返戻金が生ずるところから
「支払保険料を単に支払の対象となる期間の経過により
損金の額に算入することは適当ではない」として、
平成24 年4 月27 日をもって終身タイプの法人がん保険の保険料の
全額損金算入は廃止されました(課法2-5、課審5-6)。
新しい法人がん保険の通達による税務上の取扱は次のとおりです。
① 加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、
保険期間の開始のときから105歳までの期間の50%に
相当する期間は支払保険料の半額を損金とし、残りを資産計上とする
② 残りの期間については支払保険料の全額を損金算入するとともに、
資産に計上していた保険料を期間の経過に応じて取り崩して損金とする
例えば、35歳で法人がん保険に加入したとすれば
70歳までの35年間は支払保険料の半分しか損金に算入できない
こととなります。
理屈としては後半には全額損金算入されることになりますが
法人のがん保険の加入時の考え方として中途解約をもくろんでいる場合が
多いことを考えると、支払の都度全額損金算入ができていた従来の
法人がん保険の取扱に比べたら節税商品としての魅力は半減されたと
いうことができます。
したがって、がん保険による節税戦略を考えていた企業は
他の生命保険と比較しながら、企業の節税戦略の見直しが
必要となるのではないでしょうか。
なお、平成24年4月26日以前の契約については
旧法人がん保険の通達が適用されますので今後も
保険料の全額損金算入が認められます。
太陽光発電等の即時償却と対象者
平成24年度の税制改正に伴い、平成24年5月29日から
グリーン投資減税の定義が変更され、太陽光・風力発電設備について、
所定の要件を満たせば、現行の7%税額控除、30%特別償却に加え、
取得価格を初年度に即時償却(以下「特別償却制度」とする。)
できるようになりました。
但し、対象設備の定義は現行よりも適用可能な対象が絞られていますので、
注意が必要です。
太陽光発電では10KW以上、風力発電では1万KW以上の発電能力、
かつ、双方とも固定価格買取制度の認定を受ける必要があります。
購入を考えておられる場合は、まず、適用条件・期限・設備の内容等、
詳細を確認のうえ、手続きされることをお勧めします。
太陽光発電設備等の特別償却制度の適用を受けることができる対象者ですが、
【青色申告をしている法人又は個人が対象】となっています。(※1)
ここで問題は個人の場合です。
余剰電力の売却収入について、それを事業として行っている場合や、
他の事業の付随業務として行っている場合には、事業所得として即時償却が可能です。
しかし、不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、
これにより発電した電力をそのアパートの共用部分で使用し、
その余剰電力を電力会社に売却した場合、その収入は不動産所得となり、
たとえ買取制度の認定を受けた場合であっても、
これらの特例の適用を受けることができません。
青色申告をしている個人の方で、不動産所得として確定申告をされている方はご注意下さい。
※1
特別償却制度は事業所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税額計算における
特例になりますので、不動産所得を生ずべき資産である賃貸アパートに、
太陽光発電設備を設置し、使用する場合には適用を受けることができません。
23年度査察は192億円の脱税を把握
いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調
査され、検察当局に告発されて刑事罰の対象となる。国税庁がこのほど公表し
た今年3月までの1年間の平成23度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件
は前年度より1件少ない195件、脱税総額は前年度を約56億円下回る約192億円
だった。1件当たりでは同1,300万円少ない1億200万円。検察庁に告発した件数
は前年度より39件少ない117件となった。
平成23年度1年間に全国の国税局が査察に着手した件数は195件、継続事案を
含む189件(前年度216件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、
うち61.9%(同72.2%)にあたる117件(同156件)を検察庁に告発した。この
告発率61.9%は、前年度を10.3ポイント下回り、38年ぶりの低水準となった。
リーマン・ショック以降の経済状況の悪化により、大型の脱税事件が減少し
たことが要因とみられている。告発事件のうち、脱税額(加算税を含む)が
3億円以上のものは前年度を5件下回る10件、脱税額が5億円以上のものは同3件
下回る3件だった。
近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、23年度の脱税総額
192億円は、ピークの昭和63年度(714億円)の約27%にまで減少している。
告発分の脱税総額は前年度を約56億円下回る157億円、1件あたり平均の脱税額は
同300万円減の1億3,400万円となった。
告発件数の多かった業種・取引(5件以上)は、「建設業」が9件で最多のほ
か、「商品・株式取引」と「人材派遣業」がともに7件、「食料卸」と「情報
提供サービス」がともに6件、「運送業」と「クラブ・バー」がともに5件で続
いた。経済社会情勢を反映し、21年度15件、22年度13件と、この数年間多かっ
た不動産業が減少する一方、「食料卸」や「情報提供サービス」での告発が目
立った。
大阪・泉佐野市が「犬税」の導入を検討
大阪府泉佐野市の千代松大耕(ひろやす)市長はこのほど、犬のふんの放置が
市内の環境を悪化させているとして、その清掃等に充てる費用を賄うために、
「犬税(仮称)」の導入を検討していることを明らかにしました。早ければ2年
後にも条例を制定する方針です。総務省によると、犬税はかつて戦後の一時期
に地方税として存在していました。しかし、現在、飼い犬に対する課税を行っ
ている自治体はないということです。
犬のふんの放置問題は、都市部の自治体の悩みのタネとなっています。飼い
主にマナーやモラルの向上を求めることが第一ですが、強制力がないためにト
ラブルは後を絶ちません。泉佐野市では、2005年に環境美化推進条例を制定し
て、ペットのふんの放置やたばこの吸殻のポイ捨てを禁止しました。違反した
者には1,000円の過料を課すことにしています。しかし、実際の徴収例はなく、
アナウンス効果も上がっていないということです。
こうしたことから千代松市長は、美しいまちづくりを進めるために、今後の
2年間でマナーが改善されない場合、「犬税」を創設すると市議会に説明しま
した。税収はパトロールや清掃作業の費用に充てるということですが、具体的
な課税標準や税額はまだ明らかになっていません。
犬税は、1960年代には約2,700の市町村が導入していましたが、その後、法
定外税の整理が進み、課税団体はなくなっていました。しかし今回、再び脚光
を浴びたかたちとなったのです。
泉佐野市は人口約10万2,000人、約4万4,000世帯で、現在登録されている犬
は約5,400匹あまり。同市は、連結実質赤字比率、将来負担比率がともに早期
健全化基準以上となっており、2010年2月に財政健全化計画を策定しました。
少しでも税収を稼ごうと、今年4月に総務相の同意を得て関西国際空港の連絡
橋を利用する行為に対して課税する法定外普通税「空港連絡橋利用税」を創設
したばかりでした。
平成24年分路線価は7月2日に公表
国税庁はこのほど、平成24年分の路線価を、7月2日に全国の国税局・税務署
で公表することを明らかにしました。路線価は、相続税や贈与税における土地
等の評価額算定の際の基準となるものです。昨年7月に公表された23年分の路
線価では、標準宅地の平均額が前年を3.1%下回り、3年連続の下落となりまし
た。
路線価は、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされています。
国土交通省が今年3月に公表した今年1月1日時点の公示地価は、全国全用途
平均で前年比2.6%減と4年連続で下落しましたが、下落幅は縮小傾向を示し、
地価が上昇した地点は、前年の193地点から546地点へと大幅に増加しました。
しかし、公示地価の下落に伴い、路線価も4年連続の下落となる公算が強いと
みられています。
ところで、この路線価の公表日は、以前は8月1日でしたが、4年前の平成20
年分から1カ月も早まりました。相続税申告に必要な路線価の公表が早くなる
ことは納税者にとって歓迎すべきことではありますが、一方で、同年からは紙
による路線価図等(冊子)を国税局・税務署に備え付けないことになったので
す。公表日が1カ月短縮された理由は、冊子での路線価図等の制作をやめたこ
とで、その作業時間分が浮いたことにありました。
公表日の短縮で納税者にとっての利便性は向上しましたが、国税当局にとっ
ても、IT化、ペーパレス化によって大きなコスト削減が実現しました。平成20
年以降、国税局や税務署の窓口には、路線価図等閲覧用のパソコンが設置され
ています。混雑時は待つ必要もありますが、自宅や会社のパソコンから国税庁
のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスすれば、従来どお
り、全国の過去3年分の路線価図等を見ることができます。
国税庁『役員給与に関するQ&A』を一部改訂
国税庁は平成24 年4 月3 日、平成20 年12 月に公表した
『役員給与に関するQ&A』の一部を改訂し、"業績の著しい悪化が不可避と
認められる場合の役員給与の減額"(Q1‐2)を追加いたしました。
従来、国税庁は"業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取り扱い"の中で、
例えば、次のような場合の減額改訂は、通常、業績悪化改訂事由による改訂に
該当することになるとして、事例の列挙をしております。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての
経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、
役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの
信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、
これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
として、記載しております。
この場合の業績悪化改訂事由とは、経営状況が著しく悪化したこと等やむを得ず
役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、
通常は売上や経常利益などの会社経営上の数値的指標が既に悪化している場合が
多いものと思われます。
平成24 年4 月追加分について、
現状では数値的指標が悪化しているとまでは言えない場合にも、
役員給与の減額等の経営改善策を講じなければ、客観的な状況から
今後著しく悪化することが不可避と認められる場合は、
業績悪化改訂事由に該当するものと考えられます。
また、今後著しく悪化することが不可避と認められる場合であって、
これらの経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを
予防的に回避できたときも、業績悪化改訂事由に該当するものと考えられます。
但し、あくまでも客観的な状況によって判断することになりますから、
客観的な状況がない単なる将来の見込みにより役員給与を減額した場合は、
業績悪化改訂事由による減額改訂にあたらないことになります。
なお、役員給与を減額するに当たり、会社経営上の数値的指標の著しい悪化が
不可避と判断される客観的な状況としてどのような事情があったのか、
経営改善策を講じなかった場合のこれらの指標を改善するために
具体的にどのような計画を策定したのか、といったことを
説明できるようにしておく必要がありますので、留意してください。
がん保険節税規制の新通達の適用は4月27日
がん保険節税を規制する新通達案の適用日が注目されていましたが、国税庁
はこのほど、「がん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いを、今年4月27日を
もって廃止しました。ただし、同日前の契約に係るがん保険(終身保障タイプ
)に係る取扱いについては、「なお従前の例による」との法人契約の保険料の
取扱いを公表しました。
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)は、会社を契約者及び保険金受取人、
役員や従業員を被保険者とする契約で、一定の要件をクリアすることで支払保
険料の全額損金算入が認められていました。がん保険では、保険期間の前半に
おいて支払う保険料のなかに前払保険料が含まれていますが、かつては保険料
に含まれる前払保険料の割合が低率で、かつ、保険期間の終了に際して支払う
保険金がありませんでした。
そこで、平成13年の通達により、終身払込の場合にはその支払の都度損金の
額に算入、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入する取
扱いが定められました。しかし、10年が経過し、保険会社各社の商品設計の多
様化等により、がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合や解約返戻金の
割合にも変化がみられることから、その実態に応じて取扱いの見直しが行われ
ました。
今年4月27日以後の契約に係る保険料について適用される新通達では、例え
ば終身払込の場合、保険期間(加入時の年齢から105歳までの期間)の50%に
相当する期間までは、各年の支払保険料の額のうち2分の1を前払金等として資
産に計上し、残額を損金の額に算入することになったため、大きなメリットで
あった「全額損金算入」が「2分の1損金算入」に縮減されることになります。
なお、保険期間の50%を経過した後の期間は、各年の支払保険料を損金の額
に算入するとともに、前半で資産計上した累計額から一定の算式により計算し
た金額を取り崩して損金の額に算入します。
「財産及び債務の明細書」と「国外財産調書」
現在納税者の財産等の状況を把握するシステムとして、
年間の総所得金額等が2,000 万円を超える者には、
「財産及び債務の明細書」の提出義務が課せられています。
又、少し先になりますが、平成25年分から5,000 万円超の国外財産を
有する居住者については、国外財産の種類や数量、価額等を記載した
「国外財産調書」の提出義務制度が、平成24 年度税制改正大網に
盛り込まれました。
今回はこれら明細書等の書き方や取扱い方法について考えてみたいと思います。
① 概要と趣旨
この「財産及び債務の明細書」は、その年の12 月31 日時点において有する
国内外の財産の種類、数量及び価額、債務の金額等を記載し、
申告書に添付して税務署長に提出しなければなりません。
前年に、この明細書を提出した者には1月の下旬ごろに、
税務署から申告書とともに同明細書が送られることとなっています。
この制度の趣旨は、高額所得者は資産性所得額のウェイトが高くなる傾向があり、
保有する資産と所得に密接な関係があると考えられることから適正な課税を
確保するための補助的手段として設けられたものです。
② 歴史
ルーツは古く、昭和25 年のシャウプ勧告時に導入されいくつかの制度内容の
変遷を経て、現在も所得税法の本法(法232 条)に規定が置かれています。
③ 明細書の不提出
この「財産及び債務の明細書」は、所得税法で提出が義務付けられています。
したがって、不動産を購入したときなどに税務署から送られてくる
「お買いになった資産の買入価値などについてのお尋ね」などの
文書とは違って(お尋ね文書には回答義務はない)、
ペナルティはありません(国外財産調書制度にはある)が
提出が遅れたりすると何回か督促を受けることになります。
従って、その記載内容については相続税申告の間接的な資料として
活用される事を意識して記入する必要があります。
減価償却制度の改正について
平成23 年12 月に公布された税制改正において、
法人の減価償却制度に関する規定が改正されました。
この規定は、原則として、
平成24 年4 月1 日以降に終了する事業年度(平成24 年4 月決算)の
法人税から適用されます。
この度、国税庁からQ&A が発表されましたので、その概要を整理します。
1.定率法の償却率の見直し
① 平成24 年4 月1 日以降に取得する減価償却資産に適用される
定率法の償却率が定額法を2.5 倍した償却率(250%定率法)から
定額法を2 倍した償却率(200%定率法)に引き下げられます。
取得時期ごとの償却方法を整理すると、
● 平成19 年3 月31 日以前取得分 → 旧定率法
● 平成19 年4 月1 日以降取得分 → 250%定率法
● 平成24 年4 月1 日以降取得分 → 200%定率法
となり、取得初年度においてこれまでより20%減価償却費が少なくなります。
② ただし、改正事業年度(平成24 年4 月1 日をまたぐ事業年度)においては、
同一事業年度に取得した減価償却資産に2種類の償却率を適用する
必要が生じますので、改正事業年度に限定して平成24 年4 月1 日以降に
取得したものも250%定率法を選択して償却することができる特例が
措置されました。この選択に関しての税務署への届出は必要ありません。
③ また、250%定率法を適用している減価償却資産の償却率を
200%定率法に統一したい場合には、税務署へ200%定率法の
適用を受ける旨の届出書を提出することにより、改正事業年度又は
変更事業年度(平成24 年4 月1 日以降最初に開始する事業年度)から
償却率を統一することができます。
ただし、この場合は新たな調整計算が必要です。
この届出書の提出期限は、平成24 年4 月1 日の属する事業年度の
確定申告書の提出期限までとなります。
2.資本的支出の取得価額の特例の整備
① 平成24 年4 月1 日以降に資本的支出を行った場合には、
その追加償却資産(資本的支出)については200%定率法により
償却を行うことになります。
② ただし、旧減価償却資産(資本的支出の対象となる保有減価償却資産)が
平成19 年3 月31日以前に取得したものである場合には、
その取得価額に資本的支出の金額を加算して旧定率法による
償却を行うことが可能です。
③ 資本的支出に関しても、1の②③で記載した経過措置の特例を
受けることができます。
- 最新コラム
- カテゴリー
- アーカイブ